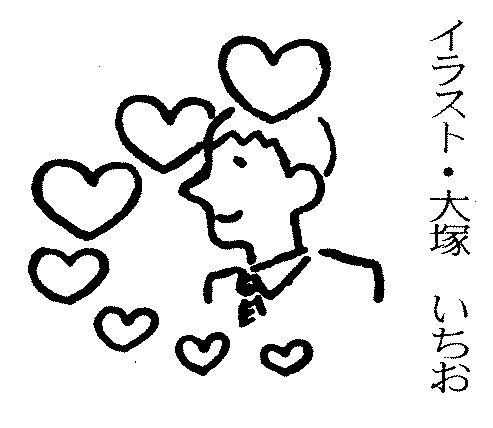新聞の「がんの最新治療を追う」と言う記事があったので、悪性リンパ腫とは関連がなかったのですが、眺めてみました。
そのコラムに、以下に引用したプラセボの記事がありました。 悪性リンパ腫もプラセボで良くなれば良いのですが、なかなかそうは行かないようです。
この記事で感じたのは、医者が強い治療をする傾向があること、また患者も強い治療を受けたがる場合もあると言うことです。 いくら口では完治しないと言っていても、どこかで完治したい、させたい、と言う気持ちが働くのでしょう。 またこれを一概に否定出来ないところに、がん治療、特に時間の経過が長い悪性リンパ腫の治療があるのではないでしょうか。
完治しない病気には、高血圧や糖尿病などの生活習慣病があります。 これらの病気は症状を抑えながら、通常の生活を送ることに最大の治療目標があります。 これと同じで、悪性リンパ腫の症状を抑えながら、つまり癌細胞が暴れださないようにコントールしながら、通常の生活を送ることを当面の目標とすべきでしょう。
そうは言っても、悪性リンパ腫では、リツキサンが出現するまでは、治療をしないと言う選択もあったのですが、こう言う選択はなかなか勇気の要ることだと思います。 こう言う場合は、プラセボ的な要するに効果がないと分かっている、治療を敢えて施すこともあるのではないかと思います。
=================================================
こころの健康学
日本経済新聞 2010年7月23日金曜日朝刊 9ページ(ライフ)
「つらい=良薬」と錯覚? 「口に苦い」偽薬は効く
前回、プラセボ(偽薬)効果について書きながら、「良薬は口に苦し」という故事を思い 出していた。これはもちろん、良い話は自分のためになるが、それだけ耳に痛い内容のことが多く、聞くのがつらいという意味だ。
出していた。これはもちろん、良い話は自分のためになるが、それだけ耳に痛い内容のことが多く、聞くのがつらいという意味だ。
確かにその意味はわかるが、この言葉を文字通りに読むとプラセボ効巣の意味に理解できなくもない。薬を飲んだときに少し苦かったり飲みにくかったりする方が、いかにも良い薬を飲んでいるような気になって、それが効果につながることが多いからだ。
こうした効果は、精神疾患の薬でも報告されている。プラセボの一種に、アクティブ・プラセボといわれるものがある。単なるプラセボが何の効果も副作用もない物質なのに対して、アクティブ・プラセボでは、効果はまったくないが、副作用だけは本当の薬と同じように表れる。効果の判定をしている本当の薬と同じように、吐き気や立ちくらみなどの副作用が出るようになっているのだ。
アクティブ・プラセボをうつ状態の患者に飲んでもらうと、驚くことに単なるプラセボ以上の効果、本当の抗うつ薬に近い効果が出ることもある。副作用を感じた患者が、本当の薬に違いないと思う分、効果が上乗せされるのだ。
こういう調査結果を見ると私たちの心の複雑さを感じる。脳の動きと働きについての研究はずいぶん進んできたが、まだまだわかっていないことがたくさん残っている。
(慶応義塾大学保健管理センター教授 大野 裕)