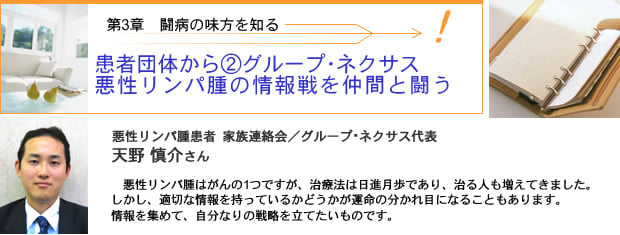濾胞性リンパ腫(ろほうせいりんぱしゅ)
更新日:2007年03月17日 掲載日:2006年10月01日
1.濾胞性リンパ腫(Follicular Lymphoma)とは
濾胞性リンパ腫は、病気の進行が比較的遅いタイプ(低悪性度)に分類され、年単位でゆっくりとした経過をたどることが多いリンパ腫です。腫れていたリンパ節が自然に小さくなったり、別なリンパ節が腫(は)れてきたりといった「波」があります。
しかし、リンパ節が腫れる以外は、微熱、体重減少、寝汗や食欲不振などの自覚症状は少ないので、気づかないうちに病期が進んでいる場合があります。そのため、頸部(けいぶ)、腋(わき)の下、足の付け根の痛みのないリンパ節の腫れ(腫脹(しゅちょう))で受診することがほとんどです。その他、健康診断などの胸部レントゲンで、肺のまわり(肺門、縦隔(じゅうかく))のリンパ節の腫れ、腹部超音波検査やCTで、腹部大動脈のまわりや骨盤内リンパ節の腫脹で見つかることがあります。
症状がほとんどないので発見が遅れ、かなり大きなリンパ節腫脹になってから見つかったり、骨髄にリンパ腫の細胞が浸潤(しんじゅん)して貧血や血小板減少の症状で見つかることもあります。他の種類のリンパ腫に比べて、リンパ節以外の臓器(例えば、胃腸、脳、肺等)にがんの浸潤を認めることはあまりありません。つまり、リンパ節に主な病変があり、診断時より病期III/IVの進行期が80%以上を占めることを特徴としています。
この病気は、日本においては悪性リンパ腫の10~15%と頻度は低いのですが、年々増加傾向にあります。比較的高年齢の方(発生のピークは60歳代)に多くみられますが、最近は30~40歳代の若い方にもみられます。経過は緩(ゆる)やかで、はじめは治療に反応しますが、何回も再発するのが特徴です。
2.濾胞性リンパ腫の診断
頸部、腋の下、および足の付け根などのリンパ節の腫脹を認めた場合には、小手術でそのリンパ節を取り出し、病理検査(顕微鏡で組織を見る)を行います。この検査をリンパ節生検といいます。また、縦隔あるいはおなかの中のリンパ節が腫脹している場合、試験的に開胸、開腹してリンパ節を取り出し、病理検査を行います。がんのタイプによって治療法が異なりますので、その結果の病理診断はとても重要です。セカンドオピニオンを求める場合にも、先方の病院で最初の標本を見てもらう必要があります。
3.治療
濾胞性リンパ腫は、抗がん剤の併用療法(いろいろな種類の抗がん剤を組み合わせること)によって大半の方でリンパ節が小さくなり、多くの方では病変がほとんど消失した状態(寛解)になります。しかし、小さくなっても再び大きくなることが多く、完全に治すことは難しい病気です。これは、進行の速い中悪性度以上の非ホジキンリンパ腫に比べると、抗がん剤がむしろ効きにくいためです。
これは抗がん剤が、分裂(1個の細胞が2個の細胞に分かれて殖えること)を盛んに繰り返す細胞に、より強い効果が出るためです。急速に進行するので早めに治療したほうがよい中悪性度以上のリンパ腫に比べ、ゆっくりと進行する濾胞性リンパ腫は分裂している細胞が少なく、化学療法が効きにくいと考えられています。そのため、抗がん剤治療が進歩したといっても、ゆっくりと進行するタイプのリンパ腫にはあまり良い治療法がありません。
従来は、弱い化学療法や放射線療法、場合によっては何も治療しないで経過をみるといった方法がとられてきました。そのうちに、途中で細胞の性格が変化して中悪性度以上のリンパ腫に変わってしまったり、化学療法や放射線療法が効かなくなってきたり、あるいは体が衰弱してしまったりという状態になることがありました。
しかし近年、抗CD20モノクローナル抗体である「リツキシマブ」の出現により、治療の方法が大きく変わってきました。リツキシマブは、CD20というB細胞の細胞表面に見られる特殊なタンパクに結合するモノクローナル抗体です。このリツキシマブはCD20陽性のリンパ腫細胞に結合し、体の免疫の防御システムを介してリンパ腫細胞を死滅させます。濾胞性リンパ腫はCD20を発現しているB細胞リンパ腫ですから、リツキシマブの効果が期待されています。
しかし、それでも残念ながら、いまだに濾胞性リンパ腫の「標準的治療」(確立した治療法として、多数の患者さんに幅広く薦めることができる治療法)は確立しておらず、どの治療を行っても現在のところ「治癒」は難しいと考えられています。そのため、治療の選択肢も多数出てくることになります。主治医およびセカンドオピニオンを通して、自分の人生設計にあった治療方法を自ら選択していくことが大切です。
1)限局期(I期、隣接病変のみのII期)患者さんの治療方針
濾胞性リンパ腫は体の一部にだけ限局した病変はまれ(10~20%)ですが、このような場合には、その部位に対して放射線治療を行うのが一般的です(領域放射線照射といいます)。放射線治療により、約半数の方に10年以上の寛解が期待でき、10年生存率は60~80%です。
しかし、10年以上たっても全身性に再発や進展を来し、生存率は平坦化しない(いつまでたっても病気が進行する)ため、限局した場合といえども治癒を得ることは困難です。また、照射部位を広範囲にしても再発を抑制する効果はなく、むしろ再発後の化学療法の実施を難しくする可能性があり、避ける必要があります。また、治癒が難しいため、高齢者などでは限局期でも病状が進行するまで経過観察をする方法がとられます。
最近ではリツキシマブと放射線の併用治療を行ったり、全身性の再発を減少させるために、放射線と化学療法を併せて使用するなどの臨床試験も行います。しかし、その結果はまだ出ていません。表1に示すような治療が、臨床研究を含めて行われています。
表1 濾胞性リンパ腫、病期I期および連続性II期の治療方針
1. 領域放射線照射(リンパ腫が存在する部位に対する放射線)
2. 症状が無い患者さんに対しては、病勢進行までの無治療経過観察(治療の延期と注意深い観察:Watchful Waiting)
3. リツキシマブ + 領域放射線療法
4. リツキシマブ単剤
5. 放射線療法併用化学療法
2)進行期(隣接病変以外のII期、III期、IV期)患者さんの治療方針
進行期濾胞性リンパ腫は、抗がん剤によって大半の方に病変の縮小効果が認められ、多くの方で病変がほとんど消失した状態(寛解)になりますが、これもまた完全に治すことは難しい病気です。平均生存期間は、10年前後とされています。
これまで「CHOP(チョップ)療法(シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)」を中心とした化学療法が行われてきました。III、IV期の濾胞性リンパ腫の患者さんの約80%で寛解が得られるものの、寛解が持続する期間は中央値で約30ヵ月と短く、ほとんどの方が再発し治癒は得られないため、平均生存期間は診断から10年前後とされてきました。
これまでの研究結果によると、症状のない場合や病気が進行する傾向を示さない場合は、 化学療法を早期に開始しても生存期間の延長効果が確認されていません。そのため、症状のない場合は、 診断がついてもすぐに治療を開始しないで、経過観察をする(Watchful Waiting)という選択もあります。ただし、病気の進行が明らかになった場合や症状が出現した場合には、化学療法や放射線療法などの適切な治療を開始する必要があります。
最近になり、B細胞だけに効果があるリツキシマブという治療薬が開発され、濾胞性リンパ腫に対する治療成績の向上が期待されています。リツキシマブの攻撃を受けたB細胞はその活動を停止して、ついには死滅してしまいます。
特殊なタンパク質のため、アレルギー(発熱、発疹(ほっしん)等)が出る場合もありますが、正常な細胞には作用しないので、抗がん剤にみられる吐き気や脱毛などの副作用がありません。また、リツキシマブは他の抗がん剤と異なり、白血球や血小板が減ってしまう副作用が少ないために、抗がん剤の投与量を減らさないで化学療法と併用することができます。
抗がん剤治療の後に再発した濾胞性リンパ腫の患者さんに、リツキシマブを週1回で4回点滴静注すると、50~60%の方に効果があることがわかりました。しかし、リツキシマブ単剤のみでは寛解となる確率は低く、現在ではリツキシマブと化学療法を併用する治療法が盛んに検討され、従来の化学療法単独よりも、治療成績が改善することが期待されています。
濾胞性リンパ腫の治療
(1) 経過観察(Watchful Waiting)
進行が緩やかであることから、特に高齢で無症状の患者さんは、無治療で経過を観察することも、治療上の選択肢となり得ます。ただし、急速な病勢の進行、発熱や体重減少などの全身症状(B症状)の出現、骨髄にリンパ腫細胞が浸潤したことによる血球減少などがみられた場合は、直ちに治療をすることが前提になりますので、外来での注意深い経過観察が必要です。診断から何らかの治療を必要とするまでの平均期間は16~72ヵ月で、中央値は3年程度といわれています。また、診断後すぐに多剤併用化学療法を開始した場合には無病生存率は有意に高くなりますが、生存率には有意差を認めていません。
(2) リツキシマブ単剤での治療成績
初発の濾胞性リンパ腫に対し、リツキシマブの週1回計4回投与(1コース)では、約50%にリンパ節縮小効果があります。効果があった場合にさらに6ヵ月ごとに計4コース繰り返すと、効果があった例は約70%に増加し、5年間病気が悪化しなかった症例(無増悪生存期間)は約35%でした。しかし、この場合も無増悪生存曲線は平坦にならず、リツキシマブ単剤での治癒は期待できないといわれています。
(3) リツキシマブと化学療法との併用の治療成績
リツキシマブ単剤では有効性に限界があるため、リツキシマブと化学療法薬の併用療法によって治療成績を改善させることが期待されています。リツキシマブは作用機序が異なるため、副作用がひどくならずに化学療法薬との併用が可能です。試験管内の実験では、抗がん剤が効きにくかったがん細胞の薬剤感受性を改善することから、両者の併用で治療効果を増強することが期待されています。
しかし現在のところ、リツキシマブと併用する抗がん剤は何がよいか明らかではなく、いろいろな薬剤とリツキシマブとの併用治療法が臨床試験で検討されています。日本では、一般的にCHOP療法(シクロホスファミド/ドキソルビシン/ビンクリスチン/プレドニゾロン)とリツキシマブとの併用療法が行われています。
他にもシクロホスファミドなどの経口アルキル化剤(欧米ではクロラムブシルが多く使われていますが、日本では保険適用がありません)やフルダラビン(日本ではリンパ腫には保険適用がありません)、クラドリビン(日本では再発例のリンパ腫にのみ保険適用があります)などのプリンヌクレオシドアナログとの併用等が行われています。
しかし、リツキシマブと化学療法の併用療法は、複数のランダム化臨床試験において奏効率および無病生存率等は改善するものの、現在までのところ生存率においては改善が認められていません。つまり、これらの治療法でも一時的な効果はあるものの「治癒」をもたらさないため、今後新規薬剤を含めた臨床研究を行う必要があります。
(a) CHOP療法とリツキシマブの併用 (R-CHOP療法)
現在、リツキシマブとの併用化学療法としては、一般的にCHOP療法が行われています。リツキシマブを2回先に投与し、その後CHOP療法を6コース中2回(3コースと5コース開始前)投与、さらに、CHOP療法終了後2回追加投与した方法では、奏効率95%、完全寛解率55%が得られ、無病生存期間も、CHOP療法のみに比べて有意に長期間であり、有効性が高いことがわかりました。
日本では、リツキシマブとCHOP療法を同時期に投与(R-CHOP療法と呼ばれています)することが、一般的に行われています(表1)。また、がん量が多くなってから(大きながんのかたまりになってから)では、R-CHOP療法の効果が低くなるということもわかってきて、がんのかたまりが小さいうちにR-CHOP療法を開始すると寛解率が高くなり、長期間寛解を維持できる可能性があることがわかりました。
しかし、治療開始9年後のデータでは、残念ながら無病生存曲線は徐々に低下しており、これも治癒をもたらす治療にはならないこともわかってきました。今までのリツキシマブを併用しない化学療法に比べると、長期の寛解が維持できますが、治癒を期待できる治療法ではないこともわかってきました。
(b) CVP(シクロホスファミド+ビンクリスチン+プレドニゾロン)療法とリツキシマブの併用
また、未治療の濾胞性リンパ腫に対して、ドキソルビシンを使用しない「CVP(シクロホスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン)療法」と「R-CVP(リツキシマブ、シクロホスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン)療法」の2つの治療を比較した検討で、リツキシマブを併用したR-CVP療法のほうが、CVP療法に比べて完全寛解率および奏効率が有意に高く、病気が進行する割合がR-CVP療法のほうが有意に低いことが報告されています。
しかし、ドキソルビシンを加えたR-CHOP療法に比べると、やや病気が進行する割合が高くなります。今後、ドキソルビシンが必要かどうかはもう少し検討する必要があります。
(c) プリンアナログ(フルダラビンやクラドリビン)とリツキシマブの併用
日本では、初めて診断された患者さんに対してのプリンアナログの使用は、保険適用が認められていません。そのため、再発された方に使用されていますが、初発患者さんに関しても、今後検討されていくと思います。リツキシマブとの併用では、免疫抑制による副作用が強く出ることがあり、感染症にかかる率が高いという報告もあります。
表1 R-CHOP療法
リツキシマブ375mg/m2、点滴投与 (CHOP)療法の前日、あるいは同日)
シクロホスファミド750mg/m2、点滴投与 第1日目
ドキソルビシン50mg/m2、点滴投与 第1日目
ビンクリスチン1.4mg/m2、静注 第1日目
プレドニゾロン100mg/body、経口投与 第1日目から5日目
表2 濾胞性リンパ腫、非隣接病変のII/III/IV期の治療方針
1. 治療の延期と注意深い観察:Watchful Waiting(症状が無い患者さんに対しては、病勢進行までの無治療経過観察)
2. リツキシマブ単独投与
3. リツキシマブと化学療法の併用
1) R-CHOP療法:リツキシマブ+シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン+プレドニゾロン
2) R-CVP療法:リツキシマブ+シクロホスファミド+ビンクリスチン+プレドニゾロン
4. 経口アルキル化剤(ステロイドを併用、または併用しない): シクロホスファミド、クロラムブシル(日本では保険適用なし)
5. 多剤併用化学療法単独
1) CVP:シクロホスファミド+ビンクリスチン+プレドニゾロン
2) CHOP:シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン+プレドニゾロン
今後日本でも行われる可能性がある治療法
6. プリンヌクレオシドアナログ:フルダラビン、クラドリビン
7. プリンヌクレオシドアナログ+リツキシマブ
1) R-F:リツキシマブ+フルダラビン
2) R-FM:リツキシマブ+フルダラビン+ミトキサントロン
3) R-FCM:リツキシマブ+フルダラビン+シクロホスファミド+ミトキサントロン
8. 放射標識されたモノクローナル抗体療法:イブリツモマブ(イットリウム-90標識)およびトシツモマブ(放射性ヨウ素131標識):再発または難治症例で骨髄のリンパ腫細胞が、25%未満または血小板数が10万以上など、骨髄予備能が低下していない症例に限る
(4) 自家造血幹細胞移植併用大量化学療法
初発の進行期には、日常的には実施すべき治療ではありません。
リツキシマブが使われる以前は、自家造血幹細胞移植を行うと生存率が延長するという報告がありました。
しかし、リツキシマブとCHOP療法の併用により、長期間の無病生存が得られるという報告が出てからは、自家造血幹細胞移植を初発から行うことは推奨されていません。その根拠としては、ランダム化比較試験でR-CHOP療法と大量化学療法との間で無病生存率の差がないこと、
また、自家造血幹細胞移植が生存期間に関しては明らかな延長を認められず、再発リスクは持続すること、濾胞性リンパ腫患者の生存率はリツキシマブなどの抗体療法により改善していること、後に骨髄異形成症候群あるいは急性白血病などの二次がんの発生をもたらすことがあるため、急性的/慢性的毒性が強い治療をルーチンに使用するだけの十分な生存率の改善が得られていないこと等があげられています。
参考文献
悪性リンパ腫治療マニュアル(平野正美、飛内賢正、堀田知光編).南江堂. 2003.
悪性リンパ腫-臨床と病理-ALTSGの研究から-.先端医学社(平野正美;監修、成人リンパ腫治療研究会;編集).2005.
http://ganjoho.ncc.go.jp/public/cancer/data/follicular_lymphoma.html#prg2